



昨年のアメリカ心臓病学会(AHA2024)に引き続き、今年は欧州心臓病学会(ESC2025)学会に参加し、研究発表をしました。
欧州心臓病学会(ESC2025)は、世界で最も権威のある循環器学会です。学術集会の会期は4日間とAHAよりも長く、参加人数は30,000人超と関連学会では最多です。今年はマドリード(スペイン)での開催となりました。
今回の注目セッションには、HFrEF患者に対する少量ジゴキシンの有効性を検討したDIGIT-HF trial、病態の安定したHFrEF患者に対するベルイシグアトの有効性を検討したVICTOR trial、急性心不全患者に対するダパグリフロジンの有効性を検討したDAPA-ACT
HF-TIMI68 trial、非閉塞性HCMに対するマバカムテンの有効性を検討したODYSSEY-HCMtrialなどの結果が含まれました。いずれもポジティブな結果は出ませんでしたが、ディスカッションをリアルタイムで聴講することにより、研究に対する考察を深めることができ、臨床のヒントを得ることができました。
今回私は口述2演題、ポスター1演題を発表しました。
①
(口述)心不全患者における尿中アルブミンの予後的価値、エプレレノンの有効性との関連について。
②
(口述)MRIのnative T1 mappingで評価した肝臓の線維化と心不全予後の関連について。
③
(ポスター)急性心不全患者における入院中のBNP変化の退院後予後への影響、エプレレノン治療との関連について。
3日間連続の発表は初めてでしたが、貴重な経験となりました。研究を御指導頂いた里見主任教授、小菅准教授、小林講師に大変感謝しております。
また、本学会で武井准教授が、劇症型心筋炎の病理学的診断と予後に関する発表をされました。心筋生検により診断を確定し、標準的心不全治療薬を導入した患者は死亡や移植のリスクが低いという、日常臨床にすぐに生かすことのできる内容でした。御留学の経験もある武井准教授の流暢な英語プレゼンテーションと質疑応答は大変勉強になりました。
さて、この時期のスペインは日照時間が長く、21時ごろまで明るいため、余暇も十分楽しめました。マドリードから電車で30分のトレドでは、歴史を感じる旧市街を散策し、レアルマドリードのサッカー観戦では現地のサポーターとともに白熱した時間を過ごしました。スペイン料理はどれも美味しく、特に海鮮をたっぷり使ったパエリアやタパスに舌鼓を打ちました。
今回の学会でも、多くの知見を得て自らの経験を増やすことができました。海外の先生とのコミュニケーションに挑戦し、また日本の他施設の先生との交流を通して、自らの臨床・研究に対する意欲もさらに高まりました。快く送りだしてくれた家族と、日々サポートしてくださる医局の先生方に心から感謝しております。
手塚絢子
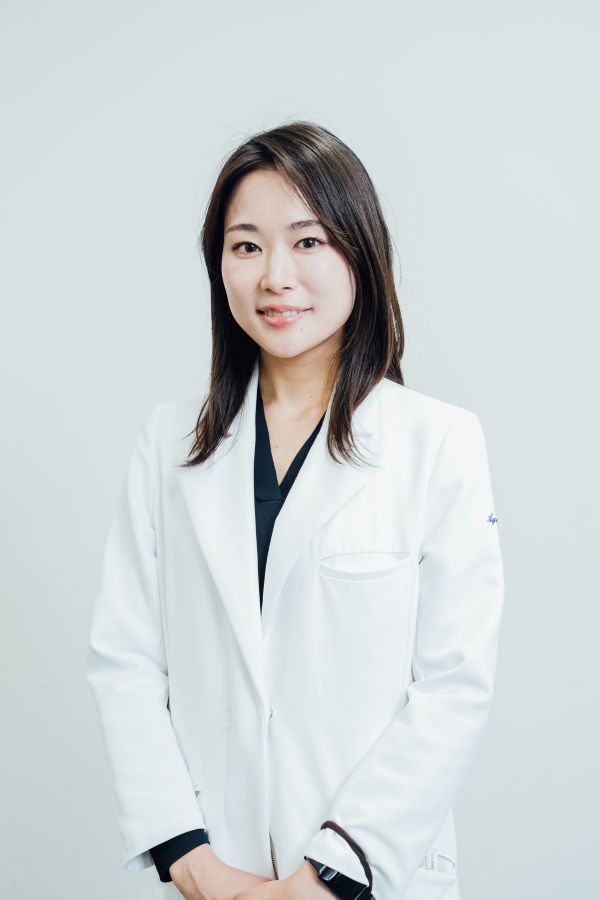
以下写真(学会の様子)にリンクします。
表示Copyright © Center for Research Administration and Innovation,
Tokyo Medical University. All rights Reserved.